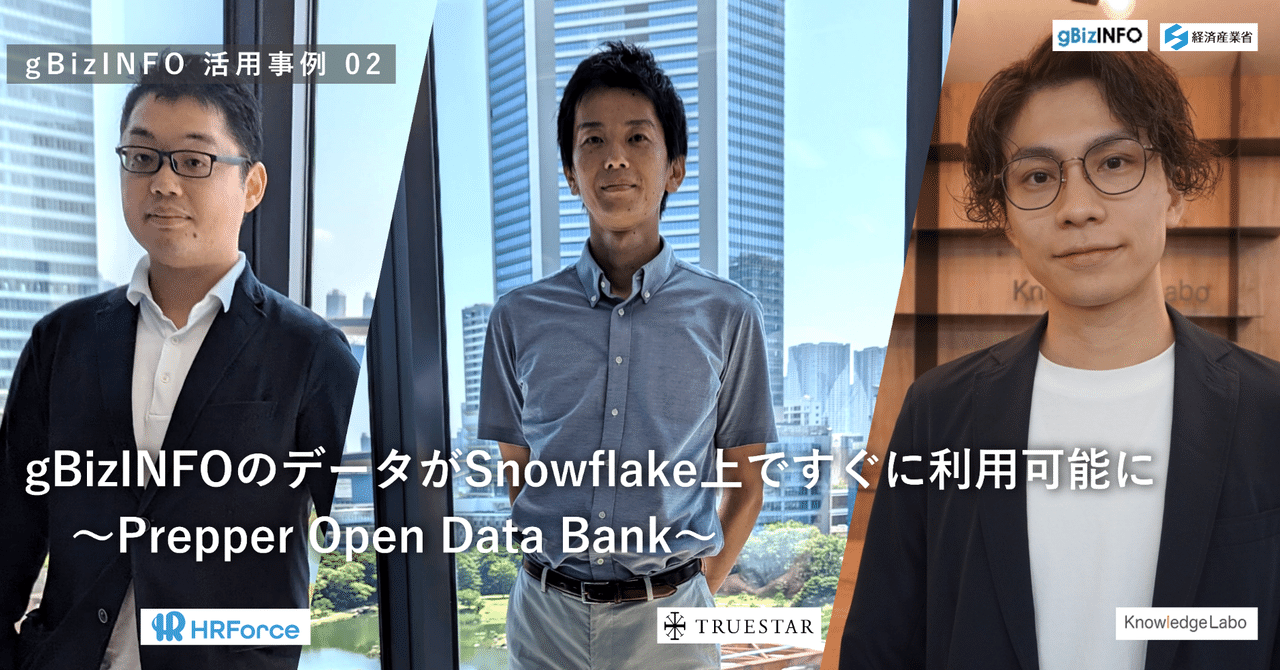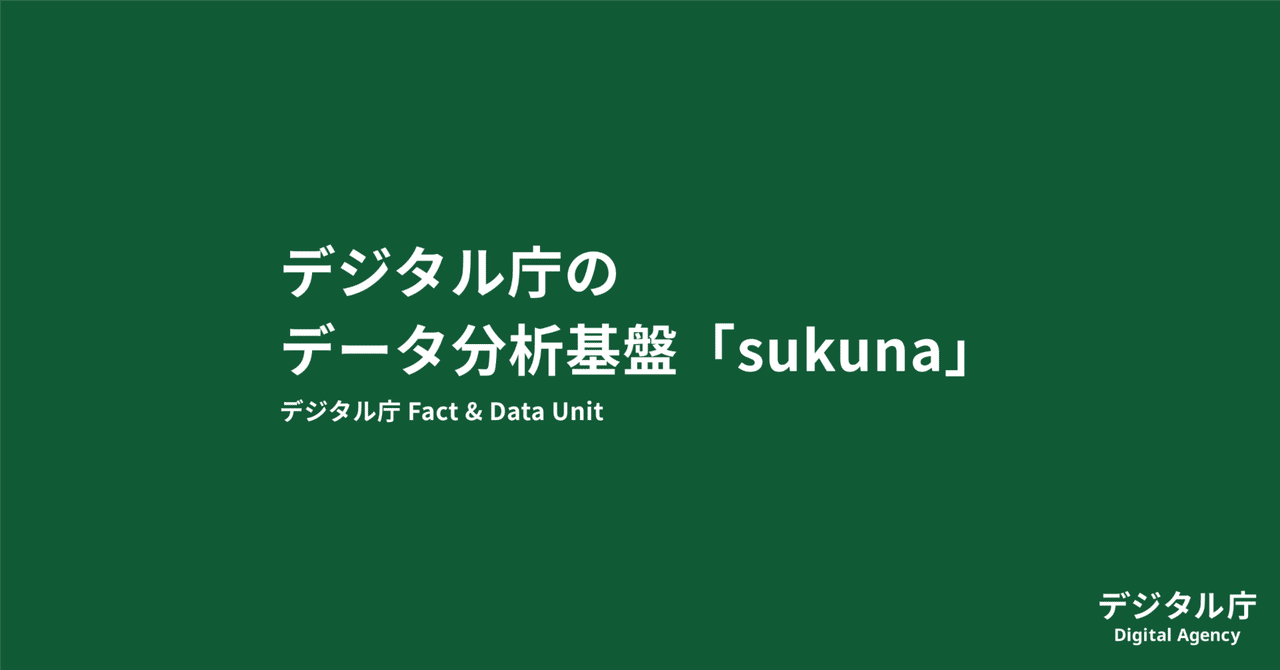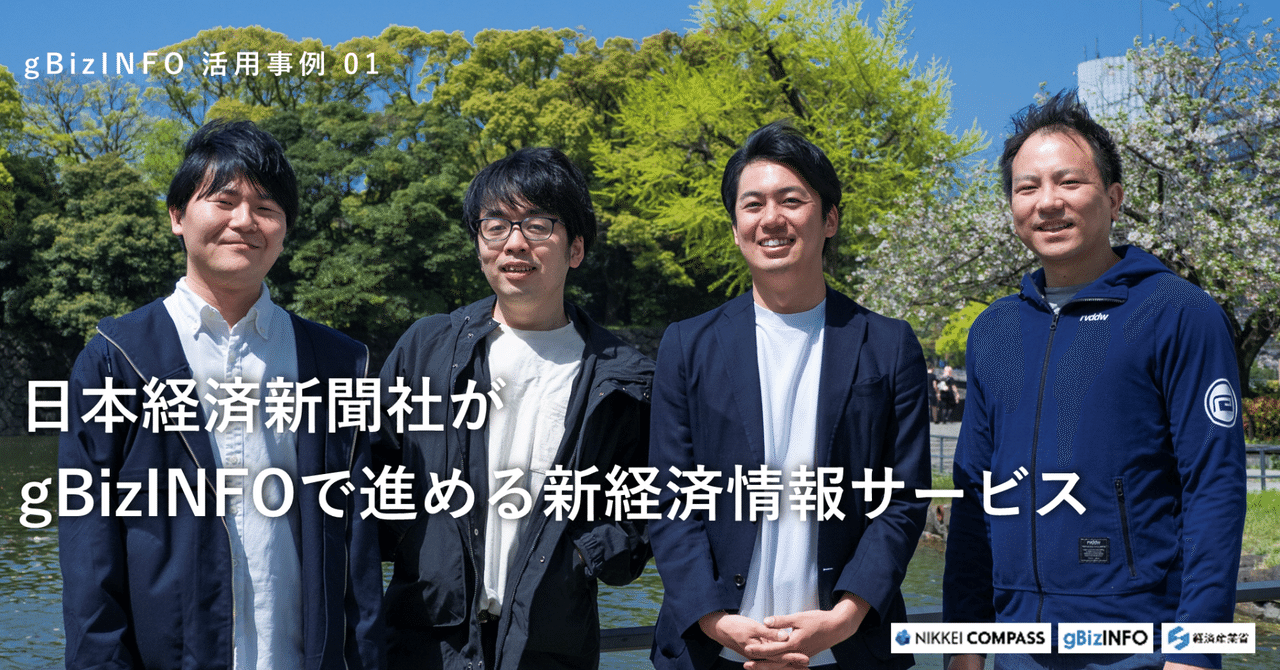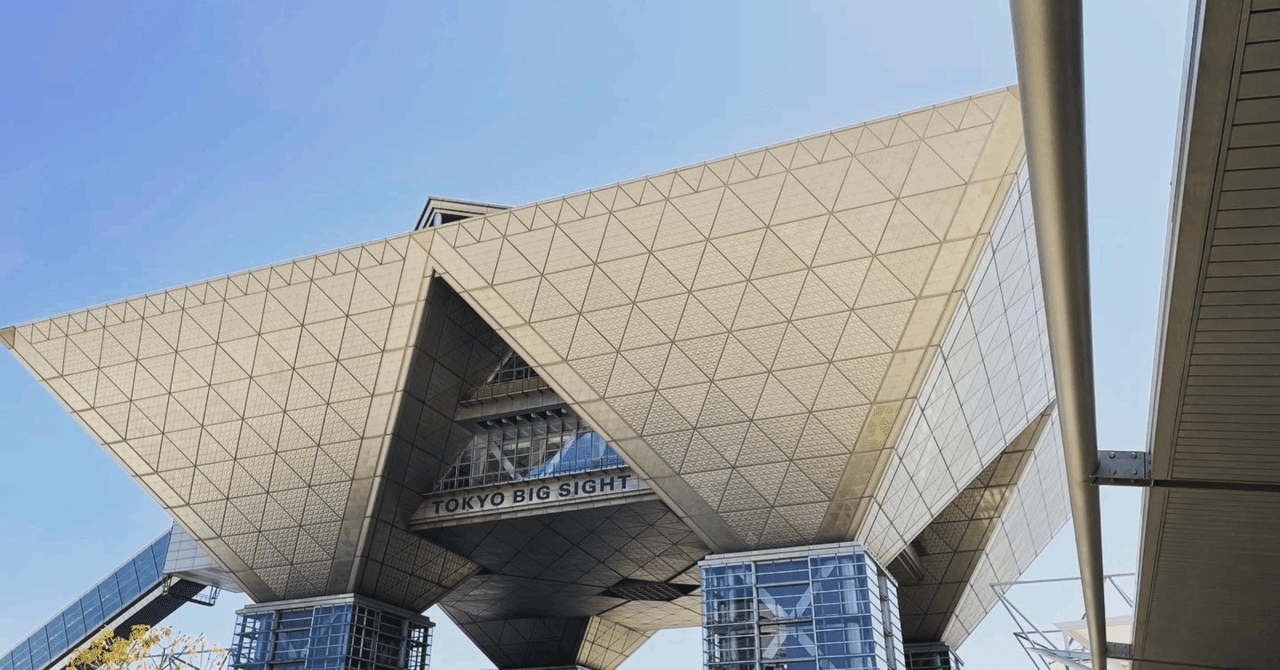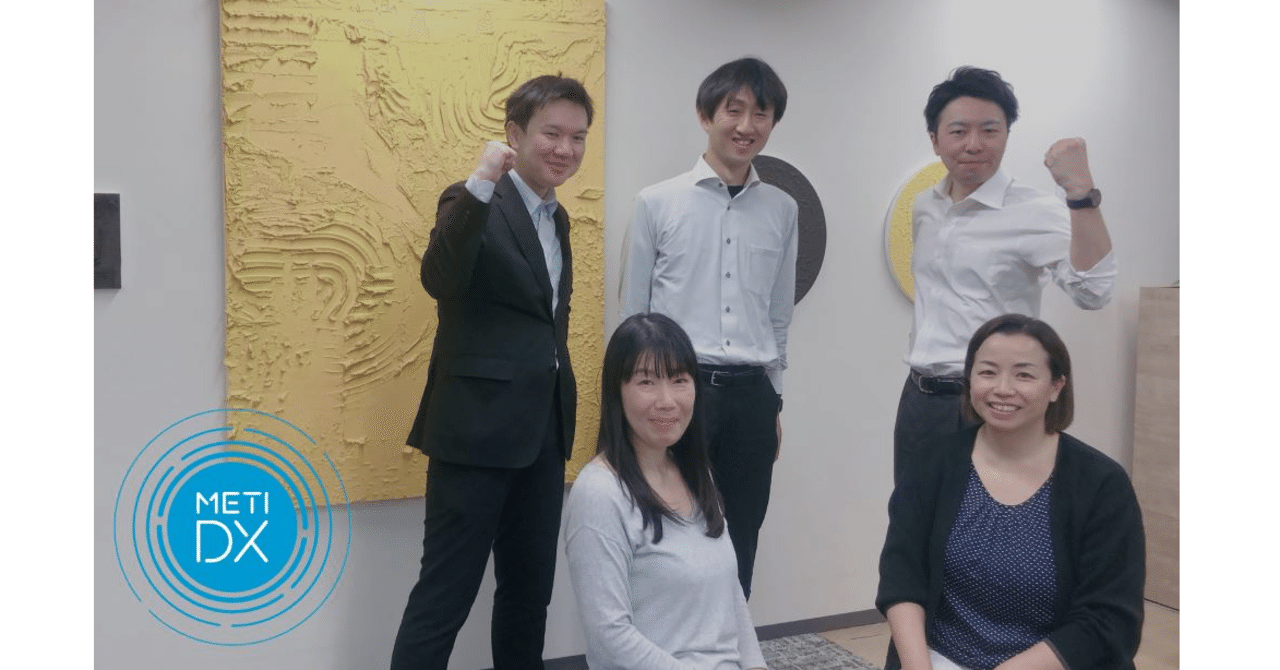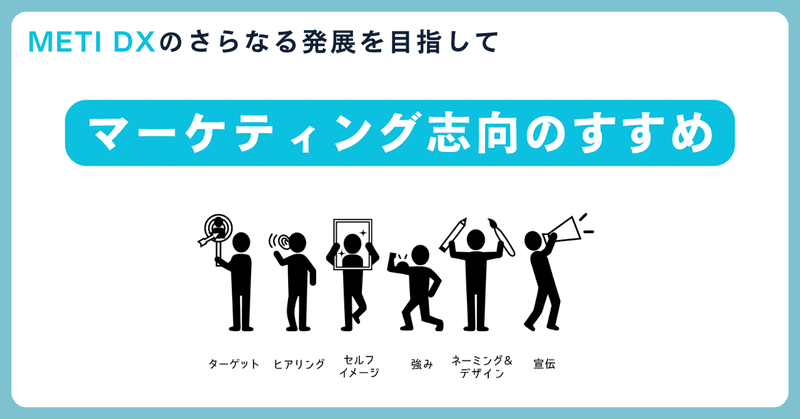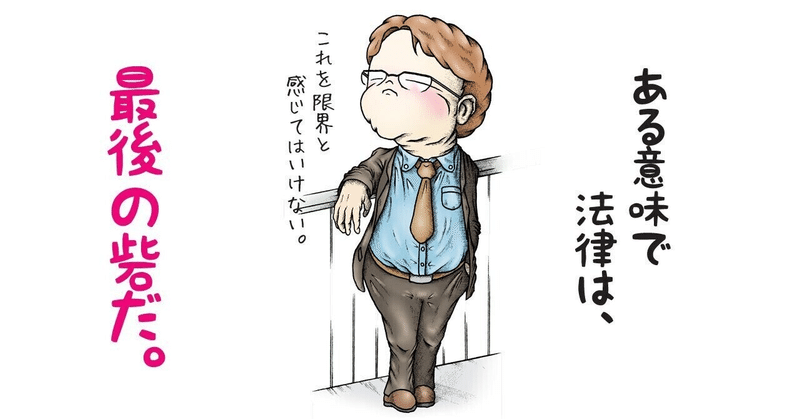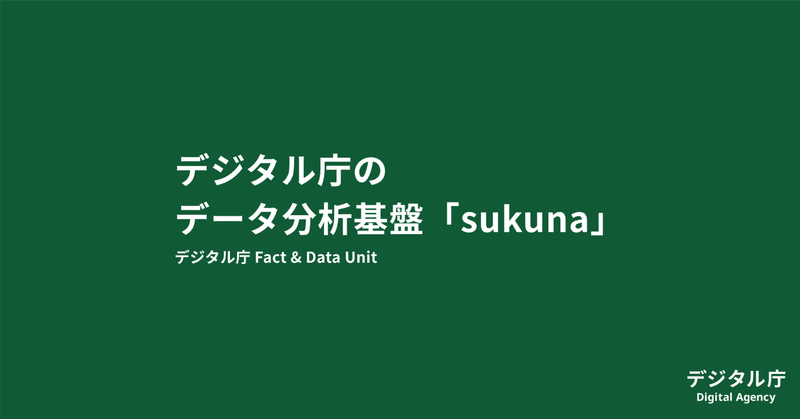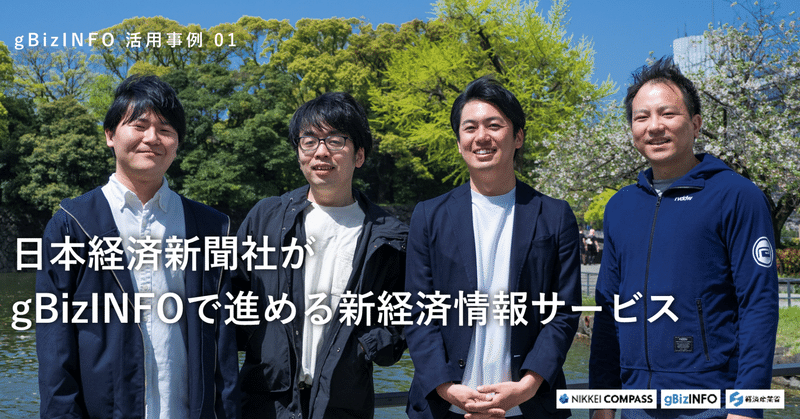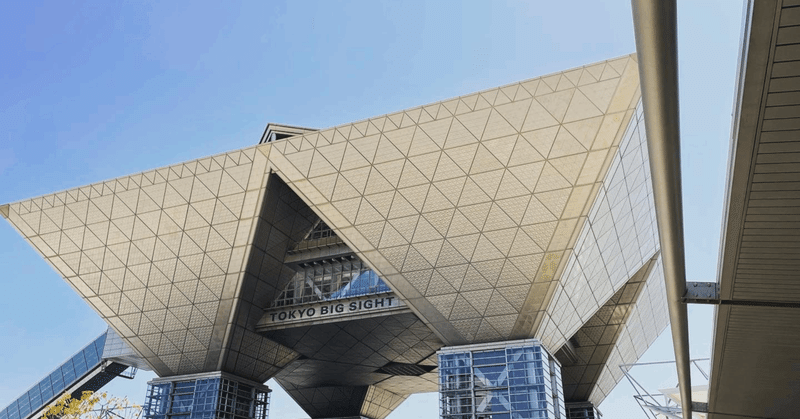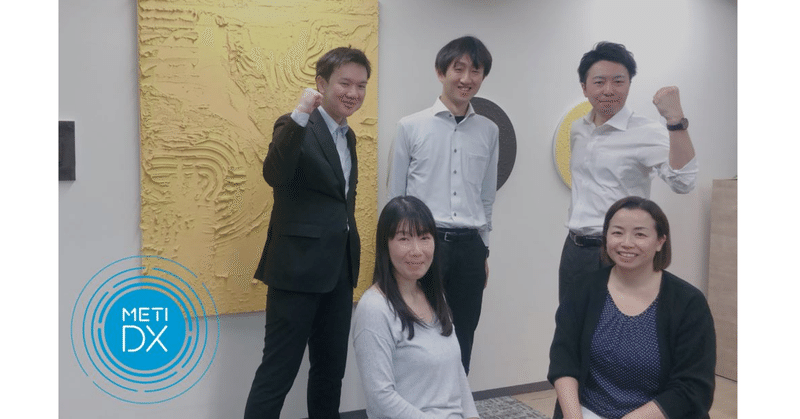METI-DX 経済産業省DXオフィス
経済産業省DXオフィスです。
経済産業省ソーシャルメディア運用方針
https://www.meti.go.jp/sns/sns_policy.html
記事一覧

【gBizINFO活用事例】デジタル庁「GビズID」分析時の法人分類に経産省の法人オープンデータ「Gビズインフォ」を利用
経済産業省DXオフィスでは、政府機関が保有する法人活動情報を法人番号で紐付けし、オープンデータとして公開するサイト「Gビズインフォ」を運用しています。 様々な法人や個人のエンジニアの皆様に、このサイトを通じて自社の事業の発展・効率化に役立てていただくため、本シリーズではGビズインフォの様々な活用事例をご紹介します。 第3回は、名前がよく似ている2つのサービス、GビズID (デジタル庁) のデジタル庁内部での分析ダッシュボードにおいて、Gビズインフォのデータを活用いただいた事
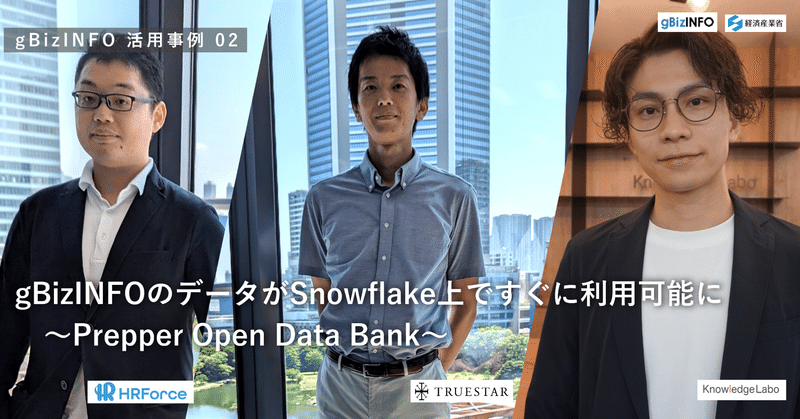
【gBizINFO活用事例】gBizINFOのデータがSnowflake上ですぐに利用可能に ~Prepper Open Data Bank~
経済産業省DXオフィスでは、政府機関が保有する法人活動情報を法人番号で紐付けし、オープンデータとして公開するサイト、gBizINFOを運用しています。全国のエンジニアの皆様に、自社の事業の発展・効率化に役立てていただくため、本シリーズではgBizINFOの様々な活用事例をご紹介します! gBizINFOとは? gBizINFOでは、政府機関が保有する法人活動情報を法人番号で紐付けし、オープンデータとして公開しております。APIの利用も可能です。詳細はこちらをご覧ください。