
経産省DXのさらなる発展を目指して ③デジタルの恩恵を受ける組織になるために
デジタル化推進マネージャーの吉田和平と申します。
現在、DX専門職員として、経済産業省内でデジタル変革の推進に携わっております。
これまで、マーケティングとデータマネジメントの重要性について記事を通じてご説明させていただきましたが、本記事では、DX推進において最も重要な要素である「組織の変革」に焦点を当ててお話しさせていただきます。
① マーケティング志向のすすめ(マーケティング編)
② 行政機関におけるデータの価値(データ編)
③ デジタルの恩恵を受ける組織になるために(組織編) ➨ 今回
古くて大きな組織をDXで変革するために最も重要な施策は、デリバリー方法の変革だと考えています。サービスをデリバリーする際には、ユーザーが求めているものを最初から最後まで徹底的に追求する姿勢が不可欠です。このためには、現行の業務の進め方を見直し、デジタル社会にふさわしいユーザー視点を取り入れたアプローチが求められます。それを実現するために、分野横断的に協力できるチームを編成し、柔軟かつ効率的に進めていくことが鍵となります。
目指すは人材循環型のフラットな組織

デジタルトランスフォーメーション(DX)を活性化させるためには、単に技術を導入するだけではなく、組織形態や文化そのものを根本的に見直す必要があります。特に大規模で歴史ある組織においては、柔軟で迅速な変革が求められるため、従来の縦割り構造では効果的なDX推進が難しいことが明確です。
まず、目指すべき組織形態は、人材循環型のフラットな組織です。従来の縦割り組織は、業務の品質向上には役立つかもしれませんが、変化に対応する柔軟性や迅速な意思決定を欠いています。DXの推進には、各部門や階層を超えた情報共有やコラボレーションが不可欠であり、そこで求められるのは、階層構造のない、対等な立場での協力を重視するフラットな組織です。こうした組織は、人材の自由な出入りが可能であり、異なる視点や知見が交流することで、想像的なアイデアや行動が生まれやすくなります。
こうした組織形態の典型例としては、スタートアップ企業が挙げられます。多くのスタートアップでは、シンプルで明確な目的を達成するために、限られたリソースやアイデアを最大限に活用し、組織内の階層や役職に関わらず必要な知見や経験を共有し合います。これにより、組織内の壁を越えたイノベーションが促進され、変化に迅速に対応する能力が高まります。スタートアップ組織のフラットな構造は、DX推進する組織単位として非常に有効なモデルとなります。
組織文化の変革
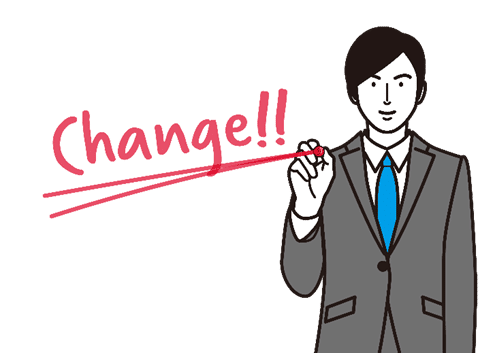
さらに、DXを進める上で不可欠なのが組織文化の変革です。DXは単に新しい技術を導入することではなく、企業文化そのものを変えるプロセスであることを理解する必要があります。既存の文化や価値観の大切な所は残しつつも、それ以外の部分については大胆に変えていかなければなりません。特に、新しい人と古い人の対話や衝突が創造的な破壊を生み出すといった観点で、変革が進むことが重要です。
私の経験からも、世間からDXが進んでいると言われている企業であっても、内情はその恩恵を享受できるのは一部の人々に過ぎず、むしろ調整業務が増え、疲弊している社員の方が多かったという実態があります。また、デジタル化を心から歓迎している人は少ないという事実もあり、こうした現状を打破するためには、新たな組織形態の導入により、デジタルに適した組織への変革の取り組みが必要です。
【事例】事業会社での経験
私が関与した事業会社では、データサイエンスを基盤にした「出島型デジタル組織」を立ち上げ、プロパー社員と新規採用社員が対等に協力する構成を取った結果、新しい組織文化が生まれました。この経験を通じて、プロパー社員と新規社員が対等な立場で協力し合うこと(数と権限のバランスを取ること)が、組織内での力の均衡を保ち、良い成果を生み出すために非常に重要であると実感しました。このような環境では、異なるバックグラウンドを持つメンバーが自由に意見を交わし、迅速な意思決定が可能になります。
しかし、この新しい組織形態を既存の組織、特に親会社のような大企業に適用することは決して容易ではありません。従来の組織文化や権限構造に根付いた慣習が障害となるため、変革を実現するには時間と努力が必要です。変革は外部から強制的に導入するものではなく、組織内から少しずつ変えていくことが最も効果的であると強く感じています。組織内のメンバーがその変革に主体的に関わり、変化を自らのものとして受け入れることが、持続可能な成功を生む鍵となります。
また、官公庁においても同様のことが言えます。例えば、デジタル庁の組織形態をロールモデルとして各省庁にそのまま適用することは現実的ではありません。各省庁が抱える独自の課題や文化、規模の違いを無視して一律に適用することは、むしろ逆効果になる可能性があります。したがって、組織改革はその組織の特性を踏まえた上で、段階的かつ柔軟に進める必要があると言えるでしょう。
現状の組織形態

また、従来の縦割り組織のままでDXを推進することは、構造的に無理があると言わざるを得ません。DXは、その性質上、不確実性や変化の速さに対応する必要があり、縦割りの枠組みでは、柔軟かつ迅速な意思決定が難しくなります。不確実な成果を追求するDXにおいては、部門間や階層を超えてスムーズに連携し、迅速な情報共有と意思決定ができる組織形態が求められます。
そのため、情報の一元化が不可欠です。組織内の情報がバラバラで断片的であれば、DXの推進は進まず、むしろ逆に効率を低下させる原因となります。情報は、全てのメンバーがアクセスできる形で一元化され、対等な立場で共有される必要があります。このような環境が整うことで、メンバー全員が協力しやすくなり、異なる視点や専門知識が交わりながら、DXの推進が円滑に行われます。結果として、DX推進の土台がしっかりと形成され、組織全体が一丸となって変革を実現できるようになります。
組織変革の進め方

そこで、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の第一歩として、現状のルールを緩和し、横断的な組織(プロジェクト)を立ち上げることが非常に重要です。縦割り組織に縛られず、異なる部門や専門性を持つメンバーが集まり、共通の目的に向かって協力できる環境を整えることが、DXを成功に導くための基盤となります。この横断プロジェクトでは、まずは効果が期待できる課題を選定し、短期的な成功体験を積み重ねることで、プロジェクトの成果を見える形で示すことが可能になります。その結果、組織内での認知度や影響力を高め、さらに積極的な参加を促すことができます。

こうした取り組みを着実に続けていくことで、初めは有期プロジェクトとして始めたものが、次第に恒久的な横断組織へと成長させます。これにより、組織内の縦横の連携が強化され、よりオープンで協力的な文化が醸成されることが期待できます。このような文化の変革が進むことで、DXの推進が組織全体に浸透し、効果的に展開されるようになります。
組織形態や文化の変革は、DX推進の中核を成す部分です。しかし、これらの変革を実際に進めていくためには、時間をかけて着実に成果を上げることが必要です。変化には段階的な進行と、少しずつ積み重ねる努力が不可欠であり、急がず一歩一歩進めることが、最終的に大きな成果に繋がります。
最後に
DXを成功させるために最も重要なのは、常にユーザー視点で考え、ユーザー満足を最大化するサービスをデリバリーするために最適な組織体制を整えることです。この組織体制こそがDX推進の土台であり、根幹をなします。ここを変革しない限り、どれだけデジタル化を進めても、DXの本質は定着せず、むしろデジタル化が業務の妨げとなる可能性があります。
再度強調したいのは、縦割り組織の枠内で行われている業務は、トップダウン型のルーチンワークであり、DX推進にはまったく適していないということです。このような組織形態の中でDXを進めようとすると、必ず構造的な歪みが生じ、変革の道は閉ざされてしまいます。たとえ優秀なコンサルタントやエンジニアを招いても、根本的な組織の問題が解決しなければ、成功には繋がりません。

DXを実現するために解決すべき真の答えは、現場にこそ存在します。現場のユーザー視点で業務を進めるには、部門横断的な組織を編成し、ユーザーと直接接することで、常に不確実性の高いユーザー課題に迅速に対応する環境を作らなければなりません。現場のニーズを反映させるためには、目標設定が現実的で具体的であることが重要であり、机上の理論やトップダウンでの施策では現場の実情に適応できません。
そのためには、ユーザー視点に基づいたマーケティングの感覚と、正確なデータを整理・活用する技術が欠かせません。このスキルを身につけることで、初めてDXの目標を明確に設定し、現実に即した施策を展開することができます。これがDX推進の核心であり、成功への道筋となります。

焦る必要はありませんが、矛盾した組織体制で業務を続けることは、着実に組織のリソースを消耗させ、モチベーションの低下や非効率な業務運営を引き起こします。組織変革はしばしば後回しにされがちですが、変革が遅れることで、手遅れになるリスクも高まります。そのため、現状を危機的な状況と捉え、早急に変革を進める必要があります。
さらに、ユーザー(国民)の信頼を損なわないためにも、コロナ禍における医療手続きや国民対応の遅れを振り返り、その教訓を活かすべきです。次の危機が発生してから手を打つのでは遅すぎます。今こそ、変革に向けた明確な計画を着実に実行し、目指すべき目標を明確にした体制作りを進めるべきです。
このような未曾有の時代においてこそ、失敗を恐れずチャレンジを続けることが最も重要な要素であると確信しています。
今回の文章を作成するうえで、私のこれまでの経験を中心に、データの重要性をご説明しておりましたが、文中の表現やロジックは以下の書籍からも参考にさせていただき取り入れておりますので、出典元としてご紹介させていただきます。
出典
・PUBLIC DIGITAL(著者:アンドリュー・グリーンウェイ)
・行政組織をアップデートしよう(著者:吉田 泰己)
・なぜデジタル政府は失敗し続けるのか(著者:日経コンピュータ)
・セブンDX敗戦(著者:ダイヤモンド社)
